-


- バークレイズ証券株式会社
代表取締役社長
- 木曽健太郎

- 木曽健太郎
- https://www.barclays.co.jp/
※ 本サイトに掲載している情報は取材時点のものです。
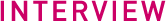
当社には約500名の社員がいますが、そのうちの45%が女性です。また、チームを任されている人やプロジェクトリーダーを含めて管理職とした場合、女性社員の中でその比率は52%に上ります。たくさんの女性が働き、たくさんの女性リーダーがいる組織と言えるでしょう。とはいえ、これは会社として意図的につくった数字ではなく、男女を問わず能力のある人材を評価した結果にすぎません。女性が活躍できる環境があることは、私たちにとってごく自然なことなのです。
バークレイズは327年の長い歴史を持つ銀行です。その昔の銀行業界では、テラー(窓口担当者)は男性だけという時代もありましたが、世界で初めて女性のテラーを採用したのもバークレイズでした。当時から女性活躍を当たり前のように推進していくカルチャーが根付いていたんです。

ビジネスシーンに良い緊張感をもたらす女性活躍
私は欧州で16年ほど勤務していた経験があり、男性より女性が多いチームをリードしていた時期も長くありましたので、社員の性差に対する特別な意識はありませんでした。女性には出産などのライフイベントがありますが、欧州では女性社員がそうしたライフイベントを終えて何度も復職し、さらに出世していくということも普通にありました。そこに女性であることの弊害はありません。そのため、日本に戻ったときに、「女性活躍の推進」や「ダイバーシティの促進」が声高に叫ばれていることに、当初は違和感があったものです。ただ、日本では欧米に比べてこの分野での取組みが遅れているのは事実でしょう。
私は今後、女性活躍やダイバーシティが日本国内でさらに推進されていくことにより、ビジネスシーンに良い緊張感が芽生えると思っています。たとえば会議の場でも、男性と女性という異なる属性を持った人達が集まることにより、様々な違った意見が出ることで、より良い結果が得られるでしょう。
女性活躍やダイバーシティを推進していく上で重要なことの一つに、「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見)の問題があります。つまり、性別や国籍などの属性に基づく先入観や第一印象で相手を判断してはいけないということです。相手が女性だからと特定の役割を期待するような考え方を排除していくことは、日本においては特に重要なことです。当社では以前から、このアンコンシャス・バイアスに対処するためのトレーニングを実施しています。
自発的なコミュニケーションを行うカルチャー
 女性活躍を推進していくために当社が行っている取組みは、ほかにも数多くあります。たとえば女性社員が妊娠したときには、マタニティ・コーチングというトレーニングを、その社員と上司を対象に実施しています。このセッションでは、たとえば上司に対しては、妊娠した社員をどうサポートしていくべきか、どういったコミュニケーションが適切なのかなどをコーチングしています。
女性活躍を推進していくために当社が行っている取組みは、ほかにも数多くあります。たとえば女性社員が妊娠したときには、マタニティ・コーチングというトレーニングを、その社員と上司を対象に実施しています。このセッションでは、たとえば上司に対しては、妊娠した社員をどうサポートしていくべきか、どういったコミュニケーションが適切なのかなどをコーチングしています。
また、ダイバーシティを促進するための社員ネットワークも盛んで、たとえばWIN(Women's Initiative Network)という団体には、社員が男女関係なく自発的に参加し、ジェンダーについて考える様々なイベントを毎月のように開催しています。最近では社内にジェンダー問題に関するライブラリーを開設したり、子供のいる社員どうしが情報共有できるチャットルームをつくったりしています。
それから有給のマタニティ・リーブの期間も長く設けており、出産前後で22週間です。併せて時短勤務やワークシェアリングなど、復職してからの働き方のオプションも多様に用意しています。そのため、出産する女性社員の育児休業の取得率、およびその後の復職率はほぼ100%です。
企業の中には、女性社員のために様々な制度を用意し、そこで満足してしまうケースもあるようです。しかし、ルールベースで女性活躍を推進しようとしても、それは根本的な解決にはなりません。必要な制度をつくるだけでなく、常に社内で議論を交わしながら、社員とのコミュニケーションを続け、マネージャー自身も変わっていくこと。私たちは女性が活躍できる環境をつくりたいのであって、女性活躍の答えをルールに基づいて定義しようとしているのではないのです。
AIよりまずは女性の活用を
 女性の中には、きめ細かい配慮ができたり、コミュニケーションが得意だったりという側面を持つ人が多くいます。チームプレーを大切にするカルチャーが根付いている当社のような組織では、そうした強みが存分に活かされる場面が数多くあります。
女性の中には、きめ細かい配慮ができたり、コミュニケーションが得意だったりという側面を持つ人が多くいます。チームプレーを大切にするカルチャーが根付いている当社のような組織では、そうした強みが存分に活かされる場面が数多くあります。
金融業界はこの数十年で目まぐるしい変化を遂げてきましたが、私自身は特に対人関係が重要な業界だと感じています。私が仕事の中で大切にしてきたことは、人との向き合い方でした。そうした観点から言っても、きめ細かい配慮ができたりコミュニケーションに長けた人材は、金融の世界に非常に向いていると感じています。AI(人工知能)の導入など業界は日進月歩ですが、まず目を向けるべきなのはAIより女性の活用ではないかと感じています。「金融女子」がもっともっと増えていってほしいですし、今後も社会の変化とともに、新しい女性のロールモデルを当社の中からも輩出していければと思っています。





 女性活躍を推進していくために当社が行っている取組みは、ほかにも数多くあります。たとえば女性社員が妊娠したときには、マタニティ・コーチングというトレーニングを、その社員と上司を対象に実施しています。このセッションでは、たとえば上司に対しては、妊娠した社員をどうサポートしていくべきか、どういったコミュニケーションが適切なのかなどをコーチングしています。
女性活躍を推進していくために当社が行っている取組みは、ほかにも数多くあります。たとえば女性社員が妊娠したときには、マタニティ・コーチングというトレーニングを、その社員と上司を対象に実施しています。このセッションでは、たとえば上司に対しては、妊娠した社員をどうサポートしていくべきか、どういったコミュニケーションが適切なのかなどをコーチングしています。 女性の中には、きめ細かい配慮ができたり、コミュニケーションが得意だったりという側面を持つ人が多くいます。チームプレーを大切にするカルチャーが根付いている当社のような組織では、そうした強みが存分に活かされる場面が数多くあります。
女性の中には、きめ細かい配慮ができたり、コミュニケーションが得意だったりという側面を持つ人が多くいます。チームプレーを大切にするカルチャーが根付いている当社のような組織では、そうした強みが存分に活かされる場面が数多くあります。