
- 宮沢勝富士
- http://www.ken-sui.jp/
※ 本サイトに掲載している情報は取材時点のものです。
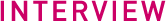
当社は群馬を拠点に、埼玉、東京、神奈川、名古屋に営業所を構え、建設業を営んでおります。その歴史は長く、2025年で59年目を迎えることができました。何より当社を際立たせているのは、年齢、性別、国籍を問わず、誰でもチャレンジができる点。建設業界の固定観念に捉われず、さまざまな挑戦を続けていきたいです。

業界で巻き起こす革新的取り組み
当社は建設業の中でも、主に防水や塗装、そしてリノベーションを手掛けています。業界の中で、当社の独自性を確立しているものは主に3点あると考えています。
まず、職人のサラリーマン化を掲げている点です。同業他社の中では委託業務も少なくない中、職人をスタッフ社員として月給制のもと直接雇用を行っています。つまり、内製化ができているという点で、強みの一つといえるでしょう。
次に、外国人実習生を多く受け入れている点です。これは最近のことではなく、先進的な取り組みとして、11、12年前から始めています。現在はベトナムやフィリピン出身の方もいますが、分け隔てなく同じ目線で楽しく仕事をしています。同じ地球人ですから、年齢、性別、国籍は問わないというのが私のスタンスです。
最後に、最前線である現場で働く女性社員も抱えているという点です。具体的にはバックオフィスで元々事務をしていた方が現場の管理者として働く事例もありました。最近では現場の管理者として女性を積極的に登用しており、賃金アップも図っています。実際、現場では当社の社員を公平かつ同じ目線で接してくれることも多く、そうしたよい環境のおかげで新たに女性が手を挙げるという連鎖が最近では多く見受けられます。
変革の端緒は素朴な疑問から
 当社は現場で活躍する女性を抱えていますが、女性登用を始めた元々のきっかけは「現場に女性がいないのはなぜだろう」と素朴な疑問を感じたことでした。確かに今までの既成概念や固定観念からいえば、建設業界は男性社会であったことは明らかです。
当社は現場で活躍する女性を抱えていますが、女性登用を始めた元々のきっかけは「現場に女性がいないのはなぜだろう」と素朴な疑問を感じたことでした。確かに今までの既成概念や固定観念からいえば、建設業界は男性社会であったことは明らかです。
一方で、当初はニーズの高さまでは把握していませんでしたが、「女性がいてもいいじゃないか」と漠然と考えていました。そして、この考えはさらに発展し、「ならば実際にまずは始めてみよう」と実行に移すフェーズになっていったのです。結果的に手を挙げた女性社員がいたため、最初のきっかけとなり、今では彼女を中心としたよい波紋が広がっているように感じます。
また、社員一人ひとりにも家族がいますから、まずはお子さんや家族を優先にしてほしいと常に伝えています。休まざるを得ないものの言い出しづらい環境は私も好きではないですし、誰にとっても避けたいもの。だからこそ、休暇を申告しやすい環境、そして周りのサポートを整えることは重要視していますし、当社の強みでもあります。
さらに、休暇だけではなく、仕事に対し相談があればしっかりと話を聞き、サポートすることも大切にしています。人が何を感じどのような意見を持つかは千差万別。人の数だけ意見の数があるのは自然なことだと考えています。特に新入社員は右も左も分からない状態では、何かを常に言われる側の立場になってしまいがちでしょう。意見を否定されるのはいい気持ちはしませんし、だからこそ私はまず耳を傾け、受け入れることを心がけています。
時には別の視点からの意見を聞くことができ、私自身の学びにつながることもあるのです。そのような社風や企業文化が浸透したことで、社員が臆することなくチャレンジしていくことにつながっているのかもしれません。今後も社員たちには、不安なく万全の状態でさまざまなことに挑戦してほしいと考えています。
絶え間ない挑戦が前例を打ち破る
 他業種他社のみならず建設業界も同様に人手不足の波が押し寄せています。その状況の中でできることは、外国からの技能実習生や女性を積極的に登用すること、もしくはIT化やDXを進めていくことで効率化を測ることだと考えています。少子高齢化、労働人口不足を少しでも解決するにはできることを全て尽くす必要がありますが、今までと同じことをし続けるだけでは何も変わりません。つまり、会社内や業界全体の新陳代謝を促し、アップデートをしたいのであれば、新たな挑戦に踏み切ることが欠かせないのです。
他業種他社のみならず建設業界も同様に人手不足の波が押し寄せています。その状況の中でできることは、外国からの技能実習生や女性を積極的に登用すること、もしくはIT化やDXを進めていくことで効率化を測ることだと考えています。少子高齢化、労働人口不足を少しでも解決するにはできることを全て尽くす必要がありますが、今までと同じことをし続けるだけでは何も変わりません。つまり、会社内や業界全体の新陳代謝を促し、アップデートをしたいのであれば、新たな挑戦に踏み切ることが欠かせないのです。
前例主義を打ち破り、刷新をしていくには若い方々や女性の視点が非常に大切です。当社のような建設業界でいえば、新たな視点を取り入れることで今までになかった革新的な建造物ができる未来もあるでしょう。そのような将来を想像することはワクワクしますし、建設業全体のみならず、日本の未来も明るくなると考えております。
さまざまな取り組みをしている当社ですが、絶対的にいいことだと信じて推進しているという感覚は実はあまりありません。それよりはむしろ、既成概念に捉われず「このような世界があってもいいのではないか」という考えの基、取り組みを実行しています。今後も明るい建設業界の未来、そして日本のため、挑戦を続けていきたいです。





 当社は現場で活躍する女性を抱えていますが、女性登用を始めた元々のきっかけは「現場に女性がいないのはなぜだろう」と素朴な疑問を感じたことでした。確かに今までの既成概念や固定観念からいえば、建設業界は男性社会であったことは明らかです。
当社は現場で活躍する女性を抱えていますが、女性登用を始めた元々のきっかけは「現場に女性がいないのはなぜだろう」と素朴な疑問を感じたことでした。確かに今までの既成概念や固定観念からいえば、建設業界は男性社会であったことは明らかです。 他業種他社のみならず建設業界も同様に人手不足の波が押し寄せています。その状況の中でできることは、外国からの技能実習生や女性を積極的に登用すること、もしくはIT化やDXを進めていくことで効率化を測ることだと考えています。少子高齢化、労働人口不足を少しでも解決するにはできることを全て尽くす必要がありますが、今までと同じことをし続けるだけでは何も変わりません。つまり、会社内や業界全体の新陳代謝を促し、アップデートをしたいのであれば、新たな挑戦に踏み切ることが欠かせないのです。
他業種他社のみならず建設業界も同様に人手不足の波が押し寄せています。その状況の中でできることは、外国からの技能実習生や女性を積極的に登用すること、もしくはIT化やDXを進めていくことで効率化を測ることだと考えています。少子高齢化、労働人口不足を少しでも解決するにはできることを全て尽くす必要がありますが、今までと同じことをし続けるだけでは何も変わりません。つまり、会社内や業界全体の新陳代謝を促し、アップデートをしたいのであれば、新たな挑戦に踏み切ることが欠かせないのです。