-


- 株式会社リンクアンドモチベーション
代表取締役会長
- 小笹芳央

- 小笹芳央
- http://www.lmi.ne.jp/
※ 本サイトに掲載している情報は取材時点のものです。
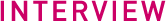
現在は国難とも言える労働力人口の減少があり、一人あたりの労働生産性を高めていく動きはどの企業にも必要とされているところかと思います。その中で、女性にも元気に活躍してもらえるような環境をつくっていくことは、会社として当然の務めでもあります。
とくに女性はライフイベントも多いため、会社や家族、男性や上司といった周囲の理解やサポートが必要不可欠です。当社としても、女性へのサポートを常に考慮していきながら、すべての働く人たちが輝ける環境づくりを推し進めていきたいと思っています。

女性の社会進出とともに成長を続けながら
当社は社名にもある通り、モチベーションにフォーカスした企業向けのコンサルティングビジネスを行っています。
創業した2000年、従業員は私を含めてわずか7名。当時は男性が5名、女性が2名という小さな会社でした。その後ビジネスは順調に推移し、すぐに中途採用をスタートしましたが、その頃から女性の応募者も多く、女性がキャリア形成を考え始めた時期と重なっています。
そして現在、創業から18年が経過し、約1400名の従業員を抱えるまでに至りました。そのうちの約650名が女性社員です。
私の見解では、女性の方が自らの専門性を極めようとする方が多いように感じています。また、会社のルールや規則に実直に取り組む方も多いのではないでしょうか。ただし男性の方がよりリーダー志向が強く、キャリアアップを目指して仕事に従事されている方が多いように思います。そのため現状では、マネジメントや管理職の比率は男性の方が多い傾向にあります。
社員と会社のエンゲージメントを高める
 とはいえ、性差によって人事を考えることは一切ありません。つまり男性の管理職比率が高いからといって、女性の管理職比率を無理に増やそうという考えは全くないということです。あくまでもそこは個々の能力の問題であり、最も大切なことは性差に関係なく社員一人ひとりが輝ける環境づくりを進めていくこと。女性の管理職比率を上げていくことよりも、会社と女性社員とのエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を高めていくことが何よりも重要なのではないかと考えています。
とはいえ、性差によって人事を考えることは一切ありません。つまり男性の管理職比率が高いからといって、女性の管理職比率を無理に増やそうという考えは全くないということです。あくまでもそこは個々の能力の問題であり、最も大切なことは性差に関係なく社員一人ひとりが輝ける環境づくりを進めていくこと。女性の管理職比率を上げていくことよりも、会社と女性社員とのエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を高めていくことが何よりも重要なのではないかと考えています。
当社では、待遇面や仕事に対する充実度、会社のビジョンへの共感や働く環境、上司との人間関係に至るまで、従業員とエンゲージメントの度合いを高めていくためのファクターを組織診断サーベイによって特定し、そのデータを一つの指針としています。これは無記名で半年に一回のペースで行っているもので、サーベイを導入してから現在まで、男女による数値の違いはありませんでした。
つまり性差に関係なく、社員一人ひとりがどれだけ納得感を持って会社とのエンゲージメントの関係を保てるかが重要であり、その納得感が表れた結果だと思っています。それこそが本質的な女性活躍の推進なのです。
男性社会が作り上げた仕組みを崩す必要性
 旧来型の日本の給与制度は、若い時に給与が安く、年齢を重ねるにつれ右肩上がりになっていくというものでした。これは男性社会が作り上げた一種の仕組みとも言えるでしょう。しかし、そうした仕組みを崩さずして女性活躍を推進しようとすれば、"女性の男性化"を進めてしまうことになるだけです。つまり、その仕組みをいかに崩すかが重要なポイントになっていると考えています。
旧来型の日本の給与制度は、若い時に給与が安く、年齢を重ねるにつれ右肩上がりになっていくというものでした。これは男性社会が作り上げた一種の仕組みとも言えるでしょう。しかし、そうした仕組みを崩さずして女性活躍を推進しようとすれば、"女性の男性化"を進めてしまうことになるだけです。つまり、その仕組みをいかに崩すかが重要なポイントになっていると考えています。
たとえば女性の皆さんが、結婚や育児、出産など、様々なライフイベントを迎えた際に仕事を離れる時期があっても、復職した時には同じ環境や給与で会社との関係を継続し、時にはライフイベント後に給与を見直し、報酬をアップさせることも必要です。
そうした抜本的な仕組みの変革をすることにより、男性も育児に専念することができるでしょうし、女性ものびのびと活躍を続けることができる。ライフイベントなどの状況変化に応じて、臨機応変に会社側が対応していくことが求められている時代なのだと思っています。
当社では女性が出産後に復職する際に、勤務する時間や日数を選べるなど、様々なオプションを用意しています。そのため復職率は100%に上ります。
また評価制度にも独自の仕組みを取り入れていて、社員に対する評価は3ヶ月おきに実施。それに合わせて賞与も年に4回支給するなど、常に状況変化に応じた評価を下せるような仕組みづくりを心がけているのです。こうした多頻度評価の導入は、創業時から続けてきたことでもありました。
今後も古い仕組みに捉われることなく、常に臨機応変な女性活躍へのサポートができる会社で在り続けたいと考えています。





 とはいえ、性差によって人事を考えることは一切ありません。つまり男性の管理職比率が高いからといって、女性の管理職比率を無理に増やそうという考えは全くないということです。あくまでもそこは個々の能力の問題であり、最も大切なことは性差に関係なく社員一人ひとりが輝ける環境づくりを進めていくこと。女性の管理職比率を上げていくことよりも、会社と女性社員とのエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を高めていくことが何よりも重要なのではないかと考えています。
とはいえ、性差によって人事を考えることは一切ありません。つまり男性の管理職比率が高いからといって、女性の管理職比率を無理に増やそうという考えは全くないということです。あくまでもそこは個々の能力の問題であり、最も大切なことは性差に関係なく社員一人ひとりが輝ける環境づくりを進めていくこと。女性の管理職比率を上げていくことよりも、会社と女性社員とのエンゲージメント(相互理解・相思相愛度合い)を高めていくことが何よりも重要なのではないかと考えています。 旧来型の日本の給与制度は、若い時に給与が安く、年齢を重ねるにつれ右肩上がりになっていくというものでした。これは男性社会が作り上げた一種の仕組みとも言えるでしょう。しかし、そうした仕組みを崩さずして女性活躍を推進しようとすれば、"女性の男性化"を進めてしまうことになるだけです。つまり、その仕組みをいかに崩すかが重要なポイントになっていると考えています。
旧来型の日本の給与制度は、若い時に給与が安く、年齢を重ねるにつれ右肩上がりになっていくというものでした。これは男性社会が作り上げた一種の仕組みとも言えるでしょう。しかし、そうした仕組みを崩さずして女性活躍を推進しようとすれば、"女性の男性化"を進めてしまうことになるだけです。つまり、その仕組みをいかに崩すかが重要なポイントになっていると考えています。